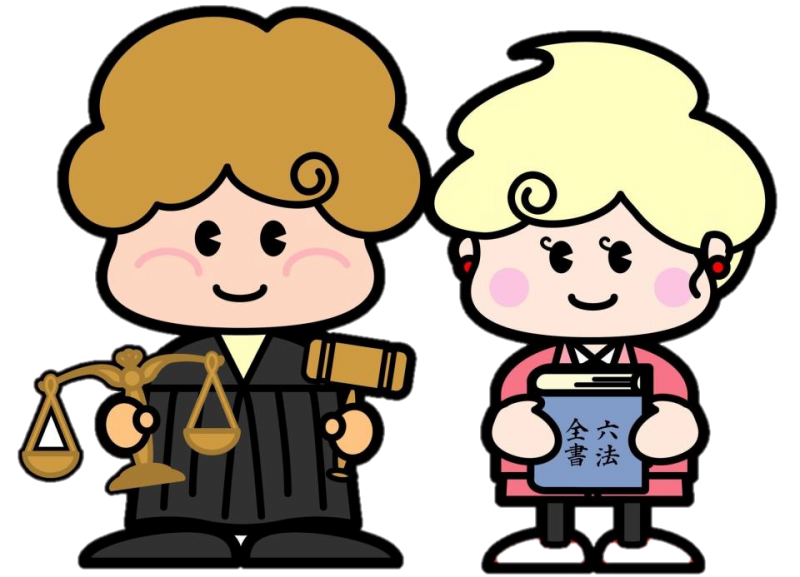昨日,読売新聞の記事から,法務省の記者会見までの数時間が長く感じられて仕方がありませんでした。
司法修習生の給費復活…ではないですが,経済的支援策についての報道がありました。
○日本経済新聞/司法修習生に生活費給付 月13.5万円、来年度から
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG19HC7_Z11C16A2CR8000/
法務省は19日、司法試験に合格した司法修習生に対し、生活費などとして月13万5千円を一律給付する新たな制度を来年度から導入すると発表した。現在は一定額を無利子で貸し、分割返済してもらう「貸与制」だが、支援策を充実させて低迷する法曹志願者の増加につなげるのが狙い。貸与制も併存させる。
司法試験合格者は裁判官や検察官、弁護士になるため司法研修所で実務研修を受ける。この間原則収入はなくなる。かつては修習生に月約20万円やボーナスを支払う給費制度があったが、財政負担抑制などの理由から2011年に貸与制に変更された。
新制度では月ごとの一律給付に加え、修習のために賃貸住宅に住む場合などに月3万5千円を上乗せする。引っ越し代も一部支払う。
法務省は制度変更に必要な裁判所法改正案を来年の通常国会に提出する。関連費用は来年度の最高裁予算案に盛り込まれる見通し。
今年の司法試験の受験者数は6899人と前年から1117人減った。
○毎日新聞/
司法修習生 月額13万5000円給付制度新設へ 法務省
http://mainichi.jp/articles/20161220/k00/00m/040/054000c
法務省は19日、裁判官、検察官、弁護士になるために司法研修所などで約1年間学ぶ司法修習生に対し、一律月額13万5000円を給付する制度を新設する方針を明らかにした。希望する修習生に国が資金を貸し付ける現行の「貸与制」を見直すことによって、経済的負担から法曹希望者が減るのを食い止める狙いがある。新制度の内容を盛り込んだ裁判所法の改正案を来年の通常国会に提出する。
改正案が成立すれば、来年度以降に修習生となる司法試験合格者から新制度が採用される予定。月額13万5000円の給付のほか、修習期間中にアパートを賃借するなど住居費が必要な修習生には月額3万5000円も給付される。現行の貸与制も貸与額を見直し、新制度と併用できる。
修習生の経済的支援を巡っては、月額約20万円の給与を支給する「給費制」が2011年、国の財政負担の軽減を理由に廃止された。代わって無利息で月額18万~28万円の貸し付けを受けられ、修習が終わった5年後から返済を10年間で完了する貸与制が導入された。
法曹希望者は、法科大学院修了者の司法試験合格率が低迷していることなどを背景に激減している。法科大学院の志願者数は04年度に7万2800人だったが、今年度は8274人。こうした状況から政府は6月、「司法修習生に対する経済的支援を含む法曹人材確保の充実・強化を推進する」と閣議決定。最高裁、法務省、日本弁護士連合会が対応策を検討していた。【鈴木一生】
司法修習生 給付金、月13万円 希望者激減で復活
http://mainichi.jp/articles/20161220/ddm/012/010/026000c
○NHK NEWS WEB/司法修習生に給付金 来年度からの導入決める
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161220/k10010812891000.html
○共同通信/司法修習生に一律月13万円 11年廃止の「給費制」復活
https://this.kiji.is/183569596283781127?c=39546741839462401
○時事通信/司法修習生に生活費給付 来年度予算に10億円 政府
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016121900865&g=soc
○弁護士ドットコム/
司法修習生に新たな「給費制」、日弁連会長「法曹志望者の確保にとって前進」
https://www.bengo4.com/internet/n_5491/
司法修習、新たな「給費制」に歓迎の声、「安心して専念できる環境を」
https://www.bengo4.com/internet/n_5490/
また,これに伴い,日弁連の会長談話も公表されました。
●司法修習生の経済的支援の制度方針の発表にあたっての会長談話
本年12月19日、法務省は、司法修習生の経済的支援策に関し、法曹三者での協議を踏まえ、平成29年度以降に採用される予定の司法修習生(第71期以降)に対する新たな給付制度を新設する制度方針を発表した。
2011年に司法修習生に対する給費制が廃止され、修習資金を貸与する制度に移行してから5年が経過した。この間、司法修習生は、修習のために数百万円の貸与金を負担するほか、法科大学院や大学の奨学金の債務も合わせると多額の債務を負担する者が少なからず存在する。近年の法曹志望者の減少は著しく、このような経済的負担の重さが法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されてきた。
司法制度は、三権の一翼として、法の支配を社会の隅々まで行き渡らせ、市民の権利を実現するための社会に不可欠な基盤であり、法曹は、その司法を担う重要な役割を負っている。このため国は、司法試験合格者に法曹にふさわしい実務能力を習得させるための司法修習を命じ、修習専念義務をも課している。ところが、法曹養成の過程における経済的負担の重さから法曹を断念する者が生じていることは深刻な問題であり、司法を担う法曹の人材を確保し、修習に専念できる環境を整備するための経済的支援が喫緊の課題とされてきたものである。
この間、多くの国会議員から、司法修習生への
経済的支援の創設に賛同するメッセージが寄せられ、また国民からも多数の署名が寄せられるなど、新たな経済的支援策の実現を求める声が高まっている。
このような状況を踏まえ、法務省が新たな経済的支援策についての制度方針を発表した意義は重要である。日弁連はこれまで、法曹人材を確保するための様々な取組を行ってきており、その一環として、修習に専念しうるための経済的支援を求めてきたものであり、今回の司法修習生に対する経済的支援策についてはこれを前進と受け止め、今後も、法曹志望者の確保に向けた諸々の取組を続けるとともに、弁護士及び弁護士会が司法の一翼を担っていることを踏まえ、今後もその社会的使命を果たしていく所存である。
2016年(平成28年)12月19日
日本弁護士連合会
会長 中本 和洋
65期から70期までの谷間の世代をどうするのか,という問題は確かに残るかもしれませんが,
貸与世代の弁護士たちが一生懸命活動した結果,経済的支援がなされるようになる(予定)であることは,
忘れてはならないと考えます。
また,私も給費最後の世代とならずにすむよう,今後も活動を続けて行こうと思います。